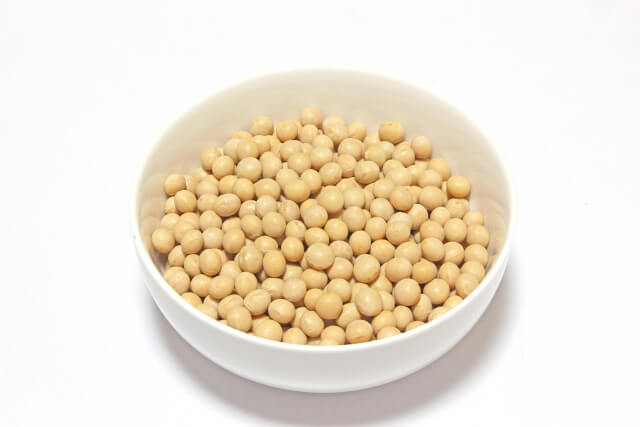イソフラボンとは、大豆などのマメ科の植物に多く含まれるポリフェノールの一種です。
その存在自体は、1930年代には知られていましたが、その構成や健康効果などは、1990年ごろから急速に知られるようになりました。女性ホルモン「エストロゲン」と似た働きをすることから、女性の美容と健康に役立つ成分として注目されています。
イソフラボンを多く含む植物は、大豆を代表とするマメ科の他に、バラ科、アヤメ科、クワ科、ヒユ科などがあり、その中でもマメ科に最も多く含まれています。
その為、イソフラボンを日常的に摂取する為の供給源は、大豆食品に含まれる「大豆イソフラボン」が最適だと考えられています。大豆イソフラボンは、別名「植物エストロゲン」とも呼ばれ、大豆一粒に対し、ほんのわずかしか含まれていない貴重な成分です。その量は全体重量の約0.2~0.4%と言われています。
また、イソフラボンには、糖と結合した「配糖体」と、糖の部分が分離した「アグリコン型」が存在しています。この2つの違いは吸収の効率にあります。
摂取した配糖体は、腸内細菌の作用などにより、アグリコン型となり、腸管から吸収されます。
配糖体も腸内細菌の作用でアグリコン型になってから吸収されますが、初めからアグリコン型になっている方が、より早く吸収されます。
このことから、初めからアグリコン型イソフラボンを摂取する方が効率的だと考えられています。
アグリコン型イソフラボンは、味噌や醤油、納豆などの、大豆発酵食品に多く含まれていますが、
近年では、日本人の食生活の欧米化が進み、大豆食品の摂取量が減少してきていることがわかっています。
イソフラボンの効果・効能
イソフラボンには、女性ホルモン「エストロゲン」に似た作用と、身体をサビさせてしまう活性酸素を除去する「抗酸化作用」があります。
この2つの作用の相乗効果で、私たちの美容や健康をサポートしてくれる優れた成分です。
現在、明らかになっているイソフラボンの効果・効能には以下のようなものがあげられます。
更年期障害の緩和

女性は閉経が近づくと卵巣のはたらきが低下し、女性ホルモンの一つである「エストロゲン」の量が急激に減少します。更年期障害の主な症状として、顔のほてりやのぼせ、頭痛などの身体的な症状や、イライラ、不安、憂鬱など、精神的なものも見られます。
イソフラボンには、「エストロゲン」の分泌を促し、これらの症状を緩和する効果があることがわかっています。
また、イソフラボンによるエストロゲンの不足を整える作用は、エストロゲンの過剰分泌が原因で引き起こされる「乳ガンの予防」につながると考えられています。
実際に、欧米に比べて大豆の消費量が多いアジア諸国の女性は、乳ガンの発症率が低いという調査結果も報告されており、その理由としてイソフラボンの摂取量が多いことだと考えられています。
骨粗鬆症の予防

イソフラボンには、骨がもろくなってしまう「骨粗鬆症」の予防にも効果が期待されています。
人間の身体は、エストロゲンの分泌が減少すると、骨にカルシウムを蓄えておく力が低下してしまいます。その結果、骨密度が低下し、骨がもろくなるため、ちょっとしたはずみで骨が折れやすくなってしまうのです。
実際に行われた研究報告があります。閉経後女性203名が、大豆イソフラボンを1日80mg とカルシウムを1日500mg を1年間摂取したところ、股関節などの骨ミネラル量の減少が緩和され、大豆イソフラボンに骨粗鬆症の予防効果が明らかになりました。
この研究では、閉経後4年以上経過したやせ型の女性や、カルシウム摂取量が少ない方に対し効果を発揮しています。※1
また、イソフラボンには骨量を増やす働きがあるため、イソフラボンの摂取量が多い人は骨密度が高いという研究結果も報告されています。
美肌効果
イソフラボンは女性ホルモンの低下による肌トラブルを予防・改善する効果があります。
年齢を重ねると、エストロゲンの分泌が減少し、肌の弾力を保つコラーゲンや、潤いを与えるヒアルロン酸をつくる機能が低下してしまいます。
イソフラボンは、エストロゲンの減少によって起きる症状を緩和する効果が期待できます。
ある研究では、年齢肌に悩む40歳前後の女性に有効的であることが確認されました。
年齢肌に悩む30代後半~40歳代前半の女性26名が、アグリコン型イソフラボンを1日40mg 摂取し、12週間継続したところ、8週間後では頬の肌の弾力が改善し、12週間後では小じわの改善が見られた
参考文献:Oral intake of soy isoflavone aglycone improves the aged skin of adult women.
また、若い方であっても生理前や排卵後はエストロゲンが減り、「プロゲステロン」というホルモンの影響を受けると、皮脂の分泌が盛んになります。それにより、ニキビや吹き出物などの肌トラブルが起こりやすくなりますので、イソフラボンを意識して摂ることが大切だと言われています。
育毛効果
薄毛は皮脂の過剰分泌や、頭皮の乾燥など、頭皮に強いダメージを受けることも原因のひとつです。
イソフラボンは「抗酸化作用」によってそのダメージを減らす働きがあることから、薄毛に効果的な成分として考えられています。
なお、イソフラボンと「カプサイシン」を同時に摂取することで「IGF-1」という物質を増やす作用が明らかになっています。
「IGF-1」が増えることで「発毛促進」や「毛髪サイクルを長期化させる」効果が期待されており、実際に行われた研究では薄毛男性の31名のうち、20名に高い発毛効果が確認されています。※2
また、イソフラボンは、男性ホルモンの過剰な分泌を抑制する効果もあります。
薄毛は、テストステロンがDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることも原因のひとつとして考えられています。そのため、テストステロンの過剰な分泌を抑えれば、脱毛ホルモンDHTが減り、結果的に脱毛の抑制に繋がります。
なお、女性ホルモンと同じような作用があるイソフラボンは、丈夫でみずみずしい艶のある髪にしてくれます。女性の場合、髪の生成を助ける女性ホルモンも上昇していくため、髪の量を増やす効果も期待できるでしょう。
参考文献
- ※1Effects of isoflavone supplements on bone metabolic markers and climacteric symptoms in Japanese women.
- ※2Administration of capsaicin and isoflavone promotes hair growth by increasing insulin-like growth factor-I production in mice and in humans with alopecia
イソフラボンの副作用
イソフラボンは身体にうれしい効果がある反面、極端に多く摂りすぎてしまうと、
以下のような副作用を引き起こす可能性があります。
- 生理不順
- 膀胱ガン
- 子宮内膜増殖症
- 乳がん発症リスクを高める
イソフラボンには生理不順を改善する効果がありますが、過剰に摂りすぎてしまうと体の中のホルモンバランスを崩す原因となり、逆効果になると言われています。
特に閉経前の女性は身体に多くのイソフラボンが取り込まれると、エストロゲンの分泌を少なく、プロゲステロンの分泌を多くしてしまいます。
これにより、PMS(月経前症候群)の症状を重くしたり、生理不順を引き起こす可能性があるのです。
また、イソフラボンの過剰摂取によってガンのような命にかかわる病気になる可能性が高まると言われています。
イソフラボンを豆腐や納豆などの大豆食品から食事として摂取する場合であればほとんど問題ないようですが、サプリメントや特定保健用食品などから取りすぎると副作用の可能性があるようです。
また、食品安全委員会は、妊婦や乳幼児などがサプリから摂取すると副作用のリスクが伴うため、食事以外からの摂取は避けたほうがいいとしています。
どのくらいの量で過剰摂取になるのか
閉経後の女性で「150mg/日」を摂取すると、子宮内膜が過度に増殖してしまう「子宮内膜増殖症」といった病気のリスクを高めることがわかっています。※1
また、閉経前の女性では月経周期に応じて血中のホルモン量が変化するため、150mgよりも少ない量でも、そのような病気になる可能性があると言われています。
副作用を起こさない摂取上限量とは

食品安全委員会では、イソフラボンの摂取目安の上限量は「75mg/日」、
そのうち、サプリメント等の健康食品からの上限量は「30mg/日」を推奨しています。
年齢や体質によってそれぞれ適用量に差があることは考えられますが、この量を目安に過剰摂取にならないように注意しましょう。
参考文献
- ※1Endometrial effects of long-term treatment with phytoestrogens: a randomized, double-blind, placebo-controlled study